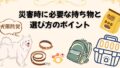災害が起きたとき、このフード、ちゃんと食べてくれるかな?
そんな不安を感じたことはありませんか?
人間の備えはバッチリ。愛犬のフードも備えてある。
そのように安心しておられる読者の方は多いと思います。
でも、普段は問題なく食べていても、環境の変化やストレスで、非常時には食べてくれないこともあります。
だからこそ、災害時に「ちゃんと食べてくれるかどうか」を意識して選ぶことが大切です。
万が一食べてくれなかったときのことも、今のうちに想定しておくと安心です。
この記事では、フードの種類と特徴、防災面ではどんな種類のフードが向いているのかをわかりやすくご紹介します。
「うちの子が、どんな時でも安心して食べられるフード」、この機会にいっしょに見直してみませんか?
犬のフードはどんな種類がある?
わんちゃんのフードには、ドライフード、ウェットタイプ、レトルト、ソフトドライがあります。
フードの特徴を知っておくと、災害時でも安心して食べられる備えがしやすくなります。
あなたの愛犬にぴったりな“非常食”、いっしょに見つけていきましょう!
ドライフード(カリカリタイプ)

とにかく軽くてコンパクトだから、避難時に持ち出しやすいのがポイント。
賞味期限も長めなので、防災備蓄のスタートにはぴったりだにゃ!
おそらく多くのご家庭で使われている「カリカリ」タイプのドライフードには、
防災備蓄に適した特徴がいくつもあります。
- 水分量が10%以下と少ないため、長期保存がしやすい
→ 賞味期限が比較的長く、数年単位の備蓄に向いている - 軽量でかさばらず、持ち運びやすい
→ 避難時の荷物として負担になりにくい - パッケージにジッパー付きが多く、再封できて衛生的
- フードのにおいが控えめで、保管場所を選びやすい
- 普段から慣れている子が多いため、非常時でも食べてくれる可能性が高い
- 水分が少ないため、別途水分補給が必要
→ 災害時は飲み水の備蓄とセットで考えることが重要 - 食欲が落ちている場合は、食いつきが悪くなる可能性も
→ レトルトやふやかしフードとの併用が安心 - 高温多湿での保存には注意が必要(特に夏場の車内など)
「どのフードを備えたらよいか迷っている」という方は、
まずこのドライフードから検討するのがおすすめです。
防災の“基本の1品”として、日常の延長線で無理なく備えることができます。
ソフトドライフード(セミモイストタイプ)

やわらかくて食べやすいから、噛む力が弱ってきた子にもやさしいフード。
個包装タイプなら、腐りにくくてローリングストックもしやすいにゃ!
ドライフードほどカリカリしていなくて、ウェットほど水分が多すぎない、中間くらいのやわらかさなのが、ソフトドライフード(セミモイストタイプ)の特長です。
- 噛みやすくて香りも強め
→ 食いつきがよく、シニア犬にも向いている - 個包装されている商品が多く、開封ごとに新鮮さを保ちやすい
- 「カリカリは苦手…」な子にも食べやすく、日常の延長で取り入れやすい
- ウェットより軽く、避難時にも持ち出しやすい
- ドライフードより賞味期限が短い傾向あり
→ ローリングストックする場合は、こまめな入れ替えが必要 - 水分を少し含む分、高温多湿の保管場所では傷みやすくなる可能性あり
「うちの子、カリカリだと食べづらそう…」と感じている方には、このセミモイストタイプは防災備蓄にもおすすめです!
ウェットフード(缶詰)

食欲が落ちがちなときでも、においにつられてパクッと食べてくれるかも。
ただし、開封後はすぐに食べ切れるように準備しておこうにゃ!
ウェットタイプの缶詰は、水分をたっぷり含み、香りも強めで嗜好性が高いのが特長です。
災害時のストレスで食欲が落ちやすい犬にとって、「食いつきのいい非常食」として備えておくと安心です。
- 水分を多く含むため、夏場の脱水対策にも効果的
- ドライフードより香りが強く、食欲がないときでも食べやすい
- 食べ慣れたごはんとは違う“特別感”で、非常時のストレス緩和にも◎
- 開封後は傷みやすく、保存がきかない(冷蔵保存が必要なことも)
- 容器が重くてかさばるため、持ち運びには不向き
- においやゴミが気になりやすい
→ 密閉袋や消臭袋と一緒に備えておくと安心 - 基本は、「1回で食べ切れる小さめサイズ」を選ぶのがおすすめ
非常時でもしっかり食べてくれる安心感は、飼い主にとっても心強いものです。
「いざというときのごほうびごはん」として、缶詰を1〜2食分加えておくと心の余裕につながります。
レトルトパウチフード

非常時でも普段に近いごはんが出せるって、うれしいよね♪
ちょっとした水分補給にもなって、食べやすさバッチリだにゃ!
軽くてかさばらない、そして保存もできる。
そんないいとこどりなのが、レトルトパウチタイプのフードです。
- 缶詰よりも軽くて開けやすい
- 常温で長期保存できる商品が多く、防災向き
- ドライフードより水分量が多く、食いつきが良い
- やわらかい食感で、食が細い犬やシニア犬にも食べやすい
- 普段のドライフードに混ぜて使うこともできる
- 持ち運びやすく、避難バッグや車中泊用の備えに◎
- 開封後はすぐに使い切る必要がある
- 内容量が少なめの商品が多く、大型犬には割高になることも
- 汁気があるため、ごみが多くなりがちで、処理に手間がかかる
「缶詰ほど重くないけど、しっかり水分もとりたい」
そんな非常時のニーズに応えられる、使い勝手のよいフードです。
ドライフードだけでは不安なときに備えて、数個ストックしておくと安心です。
備蓄のしやすさ|選びやすく続けやすいフードとは?
災害に備えて犬用フードを準備するとき、最初にチェックしたいのが「備蓄のしやすさ」です。
フード選びのカギになるのは、次の3つの視点ーー
保存期間・ローリングストックのしやすさ・保管のしやすさと価格のバランス。
この3つを意識することで、ムリなく・ムダなく・長く続けられる備えにつながります。
保存期間の長さで選ぶ

長期保存できるフードって安心だけど、お値段が高めだったり、食べ慣れてないこともあるニャン。
うちは、ふだんのフードで賞味期限が長いタイプを探して備えてるよ!
非常食としてフードを備える際に、まず注目したいのが「保存期間」です。
賞味期限が長いフードであれば、買い替えの頻度が少なくて済み、備えとして管理しやすくなります。
一方で、賞味期限が短いフードは日常で使いながら備える「ローリングストック」に向いています。
それぞれの特徴を知っておくことで、ご家庭に合った備蓄スタイルが選びやすくなります。
フードタイプ別|保存期間の比較表
非常時には「保存期間」が重要な選び方のポイントになります。
どのフードが備蓄に向いているか、以下の表で比較してみましょう。
| フードの種類 | 保存期間の目安 | 特徴(保存視点に特化) |
|---|---|---|
| ドライフード | 約1年〜1年半 | 比較的長持ち。日常的に使っている家庭が多く、買い足ししやすい。 |
| ソフトドライフード | 約6か月〜1年 | 賞味期限は短め。普段使いとの併用がしやすく、買いやすい。 |
| ウェットフード(缶) | 約2年〜3年 | 長期保存に適しているが、重くてかさばる点に注意が必要。 |
| レトルトパウチ | 約1年〜2年 | 軽量で保管しやすい。缶詰よりもやや短めの賞味期限。 |
※商品によって差があるため、購入時には賞味期限を必ず確認することが大切です。
このように、「保存期間が長い=備えに向いている」とは限りません。
ご家庭のフードの使い方や保管スペースに合わせて、どれが続けやすいかを軸に選ぶとよいでしょう。
ローリングストックのやりやすさで選ぶ

食べ慣れてるごはんを少し多めに買っておくだけで、防災の備えになるなんてラクちん♪
なくなったら買い足すだけだから、
わざわざ“非常食”を用意しなくてもOKニャン!
フードタイプ別|ローリングストックのやりやすさ比較表
非常時には「ローリングストックのやりやすさ」も重要な選び方のポイントになります。
どのフードが備蓄に向いているか、以下の表で比較してみましょう。
| フードタイプ | 賞味期限の長さ | 管理のしやすさ | 買い足しやすさ | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ドライフード | ◎ 長め(1年~2年) | ◎ 数が少なく管理しやすい | ◎ スーパーやネットで手に入りやすい | 備蓄に最も向いており、初心者にもおすすめです |
| ソフトドライ | ○ やや短め(半年〜1年) | ○ 小分けが多く数が増える | ◎ 比較的手に入りやすい | 食いつき重視の子にも向いていますが管理はこまめに |
| ウェット(缶詰) | ◎ 長め(2年程度) | △ 重くてかさばる | ○ 品揃えに差があることも | 水分補給もできるが保管スペースに注意が必要です |
| レトルトパウチ | ○ 中程度(1年程度) | △ 軽いが数が必要 | △ 取扱店が限られることも | 少量なら備えておくと便利。期限管理は忘れずに |
スタイルや犬の好みに合わせて、日常でも無理なく使えるかどうかを基準に選ぶことが大切です。
フードのローリングストックで気をつけたいポイント
- 普段から食べ慣れているフードを選ぶ
→ 非常時に食べないリスクを減らせます。 - 賞味期限を確認し、古いものから使う
→ 「先入れ・先出し」のルールを守るのがコツ。 - 在庫数を定期的にチェックする
→ 月に1回など、見直す習慣をつけましょう。 - 備蓄用と普段用を分けずに管理する
→ 特別な保管場所を設ける必要がなく手軽です。 - 保存しやすいフード形態を選ぶ
→ ドライタイプは軽くて長期保存に向いています。 - 管理しやすいパッケージを選ぶ
→ 小分けタイプやジッパー付き袋だと扱いやすいです。 - 家族全員が在庫場所を把握しておく
→ 緊急時にすぐ取り出せるように共有しておくことが大切。 - フードと一緒に必要な備品も備える
→ スプーン、はさみ、器、保存袋なども忘れずに。 - 普段は使わないフード(缶・レトルト)を備えるなら少量に
→ 試しに与えて食べるか確認しておくと安心です。 - 犬の年齢や体調の変化にも対応する
→ シニア期や病気時にはフードの種類が変わることもあるため注意。
保管のしやすさで選ぶ
保管のしやすさは、続けられる備蓄の第一歩です。
以下のポイントを押さえておくと、無理なく防災フードを備えることができます。
フードタイプ別|保管のしやすさ比較表
非常時には「保管のしやすさ」も重要な選び方のポイントになります。
どのフードが備蓄に向いているか、以下の表で比較してみましょう。
| フードタイプ | 保管のしやすさ | 開封前の保存条件 | 開封後の管理 | 備蓄向き度 |
|---|---|---|---|---|
| ドライ | ◎ とても保管しやすい | 常温・直射日光を避ける | 密閉して再保管可 | ★★★★☆ |
| ソフトドライ | ○ 比較的保管しやすい | 涼しい場所が望ましい | 傷みやすく早めに消費 | ★★★☆☆ |
| レトルト | ○ 保管はしやすい | 常温保存が可能 | 開封後は冷蔵・早期消費 | ★★★☆☆ |
| ウェット缶詰 | △ やや保管に注意 | 常温保存が可能 | 開封後は冷蔵・使い切り | ★★☆☆☆ |
フードの保管で気をつけたいポイント
- 収納スペースの確保
→ 重い缶詰やレトルトを大量に備えると、意外と場所を取ることがあります。 - 高温・湿気の対策
→ 押入れや納戸に保管する際は、風通しや除湿を意識すると劣化防止になります。 - におい対策
→ ソフトドライやウェット系は、密閉袋やケースに入れておくと安心です。 - 開封後の保存方法も想定しておく
→ 缶詰やレトルトは冷蔵保存が必要なため、停電時の扱いも考慮して「使い切りサイズ」を選ぶのがベターです。

うちはクローゼットの一角にドライフードをストックしてるよ。
軽くてにおいも気にならないから助かってるニャ!
缶詰はちょっと重たいから、たくさん備えるのは工夫が必要だね。
価格とローリングストックのバランスで選ぶ
災害用の備蓄フードを選ぶうえで、価格や日常のコスト感覚も見逃せないポイントです。
どれだけ良いフードでも、無理なく続けられなければ備えは長続きしません。
ここでは、フードの種類ごとに「コスト面での特徴」を整理し、普段使いとのバランスをどう考えるか?という視点から見ていきます。
フードタイプ別|価格の比較表
下の表では、代表的なフードの種類ごとに、コスト面での特徴や使い分けのヒントをまとめました。
コストとローリングストックのバランスを考えて、どれをどれくらい備えるかの参考にしてみてください。
| フードの種類 | 価格とローリングストックのバランス |
|---|---|
| ドライフード | 日常使いしやすく、最もコスパが良い。大量備蓄にも向いている。 |
| ソフトドライフード | ドライよりやや割高だが、食べやすく嗜好性が高い。普段との併用で無理なく備えられる。 |
| ウェット(缶詰) | 嗜好性は非常に高いが、重くかさばり、コスト面では負担が大きくなりやすい。 |
| レトルトパウチ | 軽量で扱いやすいが、使い切りタイプが多く、コスパ面ではやや不利。 |
| アレルギー対応・療法食 | 必要不可欠なフードで代用が効かない。コストは高めだが優先して備えておきたい。 |
災害に備えてフードをまとめて購入する際の視点

防災用に特別なフードを買うと、高くて続けられない…なんてことも。
でも、いつものごはんをちょっと多めにストックするだけなら、
ムリなく続けられるよ!
“備えは日常の延長”って考えると、ラクになるニャン♪
ペット用フードをまとめ買いする際は、価格や日常のコスト感覚も大切な判断ポイントになります。
まとめ買いをするときのポイントや注意点をフードの種類別にまとめました。
- 食あたりの単価が比較的安く、コスパが良い
- まとめ買いしやすく、ローリングストックに向いている
- 普段から使っている家庭が多く、継続しやすい
- 保存性・嗜好性に優れており、食欲が落ちたときの補助に向いている
- 価格がやや高めで、日常的な使用にはコストがかかる
- 賞味期限が長いため備蓄向きだが、計画的な購入と消費が必要
- 選択肢が限られ、一般的なフードより高額になりやすい
- 必要な子には、少量でも備えておくと安心
- 普段と同じフードを備蓄することが、体調維持につながる
このように、「価格が安い=正解」ではなく、自分の犬にとって必要なフードを、無理のない範囲で継続して備えられるかどうかが大切な視点になります。
避難に扱いやすいフードとは?軽さ・開けやすさ・処理のしやすさで比較
災害時は、いつもと違う環境で過ごすことになります。
避難所や車中泊など、慣れない場所で愛犬にフードを与える場面も想定されます。
そこで大切になるのが、「持ち運びやすさ」や「使いやすさ」です。
- フードが重くて持ち出せない
- 手が不自由で開けられない
- 食べ残しやゴミのにおいが強くて困った
…そんな事態を防ぐためにも、扱いやすいフードがどれなのかを事前に知っておくことが大切です。
この章では、
「軽さ」「開けやすさ」「ゴミの少なさ」「食べ残しの処理のしやすさ」
という4つの視点から、それぞれのフードの特徴や注意点をわかりやすくご紹介します。
軽さで選ぶ|持ち運びやすいフード

避難袋の中、ちょっと重たいな…って思ったら、
ドライフードに入れ替えてみてニャン!
軽くてたくさん持ち運べるのは、ほんとに安心感あるよ〜
災害時は、できるだけ荷物を軽くしておくことが大切です。
避難所への移動や車中泊の際、フードの重さが負担になることも少なくありません。
特に避難時に徒歩で移動する可能性がある方や、荷物をまとめて持ち出す必要がある方にとって、
軽さは重要な選択ポイントです。
フードの種類ごとの重さの特徴

避難するときに重いものを持って避難はできないにゃ〜。
徒歩で避難する可能性があるなら、軽いフードを選ぶのがポイントだにゃ。
フードの種類ごとに重さの特徴と備蓄に向いているのかを分かりやすく表にまとめました。
| フードタイプ | 重さの特徴 | 備考 |
|---|---|---|
| ドライフード(カリカリ) | ◎ 最も軽量。かさばらず、持ち運びに最適 | 防災バッグ・避難所持参用に向いている |
| ソフトドライ(セミモイスト) | ○ やや重め。水分を含んでいる分、ドライより若干重い | パッケージサイズや量に注意 |
| ウェットフード(缶詰) | ✕ 重い。缶が金属製で重量がある | 持ち運びには不向き。ストック用は小分け缶が安心 |
| レトルトパウチ | △ 軽めだが水分が多く、内容量によってはやや重くなることも | ドライよりは重く、缶よりは軽い。収納には柔軟性あり |
避難スタイル別のチェックポイント
- ✅ 徒歩避難・バス避難が想定される場合
→ ドライフードが基本。できるだけ軽く、小分けされているタイプが便利です。 - ✅ 車中泊・在宅避難が前提の場合
→ ウェットタイプやレトルトも選択肢に入ります。重さより「食べやすさ」や「水分補給」を重視しても◎。
開けやすさで選ぶ|非常時でも手軽に使えるフード

パウチの袋、いざって時に切れなくて大変だった…なんて声もあったんだ!
避難袋にはハサミを一本入れておくと安心かもにゃ!
災害時には、「はさみがない」「手が汚れている」「暗くて見えづらい」といった、
想定外の不便さが起こります。
そんなときに意外と困るのが、「フードの包装が開けづらい」という問題です。
片手しか使えない、視界が暗い、疲れている──。
開けやすさは、非常時ならではの大切なポイントです。
フードの種類ごとの開けやすさ
フードの種類ごとに開けやすさをわかりやすく表にまとめました。
| フードタイプ | 開けやすさ | 特徴 |
|---|---|---|
| ドライフード(ジッパー付き袋タイプ) | ◎ | 手で簡単に開封でき、再封も可能。力がいらず最も扱いやすい。 |
| ソフトドライ(ジッパー付き/小分け袋) | ◎〜○ | 基本的に開けやすいが、袋がしっかりしているタイプはやや力が必要な場合もある。 |
| ウェットフード(缶詰) | △ | プルトップ式は開けやすいが、古い缶や硬いタイプでは開封に苦労することも。缶切りが必要な場合も。 |
| レトルトパウチ | △〜✕ | 手で切れないものが多く、はさみが必要なタイプが大半。非常時にはやや不便。 |
避難スタイル別のチェックポイント
- ✅ 在宅避難なら開封器具も使えるので自由度あり
- ✅ 避難所・車中泊などでは「道具なしで開けられるか」がカギ
ゴミの少なさで選ぶ|ごみ処理の工夫ができるフード

避難中はね、“ゴミをなるべく出さない工夫”も大事な防災だにゃ〜。
レトルトは便利だけど、においが気になることもあるにゃん。
チャック付きの袋を一緒に用意しておくと、安心にゃ〜♪
避難生活では、ゴミを自由に捨てられない状況も考えられます。
とくにペットのフード容器や包装は、ニオイや量の問題で気を使う場面も多いものです。
「ゴミが少なく済むか」は、避難所や車中泊などスペースや衛生が限られる状況での重要な視点になります。処理のしやすさもフード選びの重要ポイントです
フードの種類ごとのゴミの量と処理しやすさ
フードの種類ごとにゴミの量と処理のしやすさをわかりやすく表にまとめました。
| フードタイプ | ゴミの量・かさばり | ニオイ対策・処理のしやすさ | 備考 |
|---|---|---|---|
| ドライフード(大袋/小分け) | ◎ 少なめ | ◎ ニオイが出にくく、封もできて清潔 | ジッパー式なら再封可能で管理しやすい |
| ソフトドライ(小分けパック) | ◎ とても少ない | ◎ かさばらず清潔に捨てやすい | 小分けなので管理しやすく衛生的 |
| ウェットフード(缶詰) | ✕ 多い・重い | ✕ ニオイが強く、密閉袋での処理が必要 | 缶がかさばるためゴミ処理が大変 |
| レトルトパウチ | △ 少なめ | △ 汁気で汚れやすく、ニオイが残りやすい | 二重袋や密閉袋での処理が安心 |
避難スタイル別のチェックポイント
- ✅ 在宅避難なら家庭ゴミで処理できるが、断水時は袋の密封が必須
- ✅ 車中泊・避難所では「軽くて処理しやすい包装」がストレス軽減につながる
食べ残しの処理のしやすさで選ぶ|片付けやすいフード

災害のときは、“ちょっと少なめにあげる”のがコツだニャ〜。
食べ残しが少なければ、片付けもラクだし、衛生的にも安心にゃん♪
災害時は、洗い物ができない、ニオイがこもる、ごみ処理が難しいなど、日常とは違った不便があります。
そのため、「食べ残しをどう処理するか」も、フード選びの大切な視点です。
特に避難所や車中泊では、汚れたフードをそのまま放置すると、衛生面やニオイのトラブルにもつながりかねません。
フードの種類ごとの片付けやすさ
フードの種類ごとに片付けやすさをわかりやすく表にまとめました。
| フードタイプ | 片付けやすさの評価 | 理由・補足説明 |
|---|---|---|
| ドライフード | ◎ 処理が簡単 | 食べ残しても乾燥していて、ニオイが出にくく処理しやすい |
| ソフトドライフード | ○ 比較的簡単 | やや湿っているがベタつきが少なく、比較的片付けやすい |
| ウェットフード(缶詰) | ✕ 処理が難しい | 水分が多く、残すと腐敗やニオイの原因になりやすいため、すぐに処理が必要 |
| レトルトパウチ | △ やや注意が必要 | ウェットほどではないが、水分・汁気でニオイが出やすく、早めの処理と密封が推奨される |
災害時に意識したいポイント
- ✅ できるだけ食べきれる量を与える
- ✅ 食べ残しは新聞紙や吸水シートで包み、密封できる袋に
- ✅ フードの形状(ドロドロ・かたまり)で片付けやすさが変わる
犬の体調に合った非常食の選び方|食べやすさ
災害時の環境は、犬にとってもストレスの多いものです。
そんなときに、「食べづらい」「体調に合わない」フードしかないと、
食事そのものが負担になることもあります。
とくに高齢犬や持病のある子、食が細い子には、いつも以上に体にやさしいフード選びが大切です。
この章では、「水分量」「アレルギー対応」「年齢・体調への適応」「混ぜて慣らせるかどうか」という4つの視点から、災害時でも犬が安心して食べられるフードの選び方について整理します。
水分量|暑さや脱水対策を意識した備えを

夏の暑さで、のどがかわいてても水を飲まないワンちゃんもいるニャン…!
そんなときは、水分たっぷりのレトルトごはんや、ふやかしたドライフードがおすすめニャン。ごはんから水分もいっしょにとれたら、脱水対策にもなるニャン♪
非常時には、ストレスや環境の変化で水を飲む量が減ってしまう犬もいます。
特に夏場や車内避難のような高温環境では、脱水リスクが高くなるため、水分を多く含むフードが有効です。
- ウェットタイプやレトルトタイプは、水分が70〜80%と豊富。
- 普段から水をあまり飲まない子には、水分ごと摂れるフードを選ぶと安心。
- ドライフードを使う場合でも、少しお湯でふやかすだけで水分摂取量を増やすことができます。
アレルギー対応|「いつもと同じフード」がいちばん安全

アレルギーのある子は、知らないフードでおなかをこわすこともあるニャン…!
だからこそ、防災用にも「いつも食べてるフード」を少し多めにストックしておくのが安心ニャン。非常時こそ、慣れたごはんが一番の安心ニャンよ♪
アレルギーのある子にとって、いつもと違うフードは体調悪化のリスクがあります。
非常時でも安心して食べられるよう、普段から食べ慣れているアレルゲンフリーのフードを備えておくことが大切です。
- アレルギー対応フードは価格が高めなので、少量でも備蓄しておくと安心です。
- 原材料の表示やパッケージの見直しも忘れずにしておきましょう。
- 災害時は獣医に相談できないこともあるため、安全性が確認されたフードを選ぶのがポイントです。
犬の年齢・体調|シニア犬・病気の子はとくに配慮を

シニアの子や病気のある子は、かたいフードが食べにくかったり、体に合わなかったりするニャン…!やわらかくて食べやすいものや、療法食・処方フードの備えが大事ニャン。
シニア犬や病気のある子は、噛む力や消化能力が落ちている場合があります。
こうした子にとっては、固いドライフードよりもやわらかく消化しやすいフードが適しています。
- ソフトドライやウェット、レトルトタイプは咀嚼が弱くても食べやすい。
- 持病がある場合は、療法食を少しでも備えておくと安心です。
- 体調に合わせて与え方や量を調整できるよう、個包装タイプも便利です。
【まとめ表】犬の体調に合わせた非常食のポイント
水分量、アレルギー対応、年齢・体調の視点で、どのフードが適しているか、配慮すべき内容を表にまとめています。
| 視点 | 配慮すべき内容 | 適したフードタイプ |
|---|---|---|
| 水分量 | 脱水対策として水分を一緒に摂れるものが安心 | ウェット、レトルト、ふやかしドライ |
| アレルギー対応 | 原材料やアレルゲンのチェックが必要 | アレルギー対応フード、療法食 |
| 年齢・体調 | 噛む力・消化力に合わせてやわらかさや成分を調整 | ソフトドライ、ウェット、レトルト、療法食 |
こうした工夫をしておくと、災害時でもスムーズに食事ができ、犬のストレスや体調不良を予防することにもつながります。
災害時でも食べてくれる?普段から味に慣らしておく工夫が大切
非常時はいつもの環境と大きく異なり、犬にとってはそれだけで大きなストレスになります。
そんな中で普段と違うフードをいきなり与えても、警戒して食べてくれないということは珍しくありません。
特に、嗜好が強い子や神経質な性格の子は、ちょっとしたにおいや食感の違いだけでも食べなくなることがあります。
「いざというとき、せっかく備えたのに食べてくれなかった…」という事態を防ぐために、普段から“慣らしておく工夫”が大切です。
複数のフードを混ぜておく|“初めての味”をなくすポイント

非常時に、せっかく用意したのに“食べてくれない”なんて悲しいよね…。
だから、普段からちょっとずつ混ぜて慣らしておくのがポイント!
いろんな味に慣れておけば、いざというときも安心だよ♪
普段のごはんに、非常食として備える予定のレトルトフードやウェットフードを少しずつ混ぜて慣らしておくのがベストです。
いきなり切り替えるのではなく、少量ずつ混ぜていくことで、においや味、食感の変化に慣れていくことができます。
また、いろんなフードを順番に食べさせておく「フードローテーション」も有効な手段です。
何種類かのフードに慣れておくことで、「初めての味」や「慣れない食感」のリスクを減らせます。
混ぜてもいいケースと注意点

フードを混ぜるのは、切り替えや食いつきアップのときにおすすめだよ♪
でも、急にたくさん混ぜるとお腹に負担がかかるから注意!
少しずつ慣らすのがコツだよ〜🐾
フードを混ぜて与えるのは、次のような目的があるときに有効です:
- フードの切り替えをするとき(いきなり変えるよりスムーズ)
- 食いつきを良くするとき(トッピングのように活用)
- 栄養バランスを補うとき(不足している成分を加える)
ただし、混ぜる際にはいくつか注意点もあります。
- 消化に負担がかかる組み合わせは避ける(例:油分の多い缶詰+高脂質ドライフード)
- 保存性の違いに注意(乾燥フードと水分の多いフードを混ぜると傷みやすくなる)
- 愛犬の体調や持病に合ったものを選ぶ(腎臓病・アレルギーなど)
混ぜること自体は悪いことではありませんが、「何を・どれくらい・どんなタイミングで」混ぜるかを意識して、安全に与えることが大切です。
まとめ|愛犬が安心して食べられる非常食を、今のうちに見直そう
災害時、愛犬がいつものようにごはんを食べてくれるかどうかは、安心して過ごすための大切な要素です。
非常時はストレスや環境の変化から、食欲が落ちたり、普段のフードを食べなくなったりすることもあります。
この記事では、
- フードの種類ごとの特徴(ドライ・レトルトなど)
- 「軽さ」「保存性」「食べやすさ」など選ぶ11の視点
- アレルギーや体調など、犬ごとの体への配慮
- 季節や家庭環境に応じた追加備え
といった内容を幅広く紹介しました。
ポイントは、「特別なフードを買う」のではなく、「日常の延長で備える」こと。
ふだんから少し多めにストックしておく「ローリングストック」を取り入れることで、無理なく備えを続けることができます。
災害時は、人間同様わんちゃんもストレスを抱えます。そんな時でも複数のフードを食べられるようにしておくことが安心につながります。
災害時にいきなり対策をすることは難しいので普段から複数のフードを試しておくことがいちばんの対策になるでしょう。
大切な家族の一員である愛犬のために、
「いざというときに安心して食べられるごはん」を、今のうちに見直しておきましょう。
関連記事
避難スタイル別に選ぶ犬のフード|車中泊避難・避難所・在宅避難・ホテル避難の備え方
【在宅避難に備える】災害時のペットの水・フード・衛生対策まとめ― 犬・猫・小動物別に必要量と注意点を解説