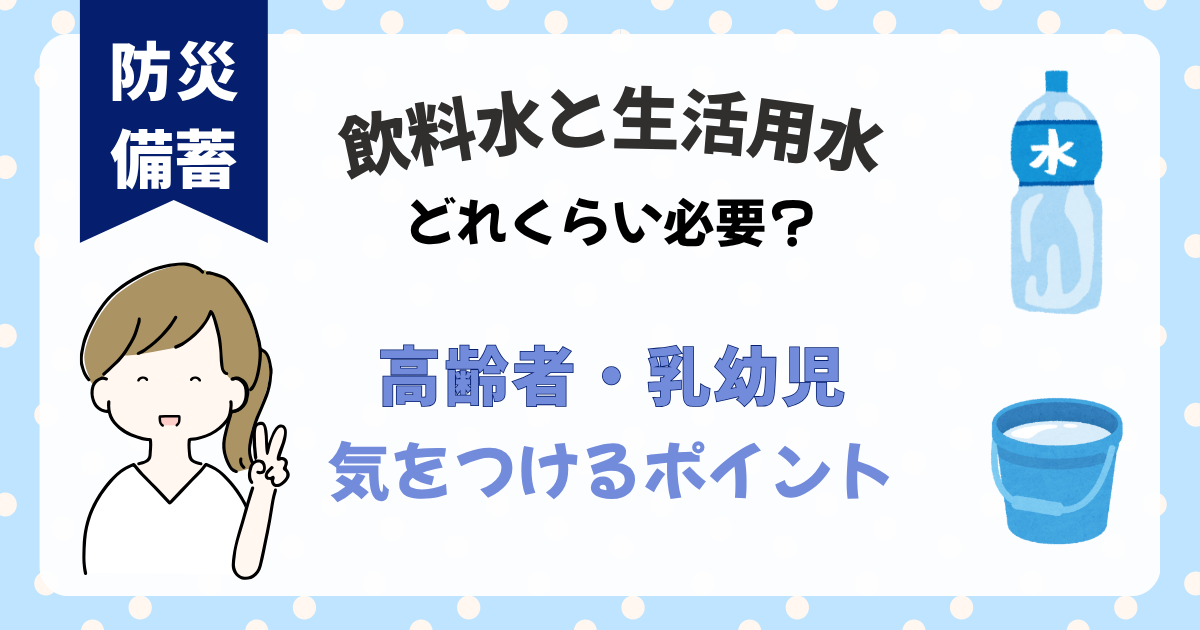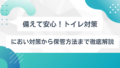災害時の「水の備蓄量」は、季節や家族構成によって変える必要があります。
特に高齢者や乳幼児がいるご家庭では、体調やケアの面からも特別な配慮が欠かせません。
この記事では、飲料水と生活用水の備蓄量の目安、夏場・冬場の注意点、そして高齢者・乳幼児がいる家庭の備え方について詳しく解説します。
「家族の人数別」「ペットボトルのサイズ別」に必要な備蓄量を表でまとめているので、
ご自宅に合った備え方の参考にしてください。

水の備蓄量がひと目でわかる!
家族の人数とペットボトルのサイズ別に、必要な本数・ケース数を表にまとめましたんだにゃ。
この記事を読めば、
- 災害時に必要な飲料水と生活用水の量
- 夏と冬で変わる備蓄のポイント
- 高齢者や乳幼児がいる場合の注意点
が、わかるようになります。
なぜ「水」の備蓄が重要なのか
災害が発生したとき、一番先に困るのが「水の確保」です。
飲む・調理する・衛生を保つ——日常生活のあらゆる場面で欠かせない水は、
命を守る最も基本的なライフラインです。
この章では、
水がないとどれほど生活が制限されるのか、
断水の復旧がどれだけ時間を要するのかを、過去の事例をもとに解説します。
在宅避難を前提とした備えの重要性についても見ていきます。
災害時「水は命そのもの」

災害が起きると店舗の商品は売り切れになるにゃー。
給水車は長蛇の列になることがあるにゃー。
災害が発生すると、多くの人が最初に困るのが「水が手に入らないこと」です。
たとえば、
- のどが渇いても飲み水がない
- トイレが流せない
- 手や顔が洗えない
- 食材が洗えず調理もできない
- 傷の手当てや消毒ができない
このような状態は、想像以上にストレスになり、健康被害につながりかねません。
しかも、店舗の商品は、水を含め売り切れ状態になり、手に入れることが難しくなります。
また、給水車が来ても長蛇の列に何時間も並ぶことになることが多いです。
自宅から給水車までの距離が長かったり、
高齢者や体調の悪い人にとっては、それだけで大きな負担です。
実際の災害でも、
「食べ物より水がなくて困った」
「トイレが使えず衛生面で本当に大変だった」
という声が数多く聞かれます。
普段当たり前に使っている水ですが、
「命そのもの」と言う自覚を持っておきたいものです。
断水の復旧にはどれくらいかかる?

断水の復旧には、数週間かかることもあるにゃ。
東日本大震災のときは、1か月半も水が出なかった地域もあったんだにゃ〜。
「断水しても、数時間で水が出るだろう」と思っていませんか?
実際には、数日〜数週間も復旧にかかることがあります。
たとえば、地震では地盤のゆがみや水道管の破損により、広範囲で断水が発生します。
台風や豪雨でも、浄水場の機能が止まってしまったり、配管のトラブルで、水が止まることがあります。
以下は、過去の大災害における断水状況と復旧の目安です。
| 災害名 | 最大断水戸数 | 完全復旧までの目安 |
|---|---|---|
| 阪神・淡路大震災(1995) | 約120万戸 | 約3か月 |
| 東日本大震災(2011) | 約260万戸 | 約1か月〜1か月半 |
| 熊本地震(2016) | 約44万戸 | 約3週間程度 |
復旧が遅れる理由には、
- 水道管が破損する
- 被災エリアが広くて、作業員や資材が足りない
- 道路が寸断して給水車や復旧作業車が通れない
- 医療機関や避難所の復旧が優先されるので、一般家庭は後回しになる
などの理由があります。
建物が無事でも、水道水が使えないと日常生活は大きく制限されます。
だからこそ、普段から「断水が長引く前提」で備えておくことが大切なのです。
在宅避難の人は「水の備蓄」は多めにしよう

在宅避難を考えるなら、水の備蓄だけでなく、給水所までの行き方も事前に調べておこうね!
「避難所に行かず、自宅で過ごせるなら安心」と思う方は多いかもしれません。
でも在宅避難をするつもりなら、水の確保は事前に準備しておく必要があります。
災害が起きると、電気やガスと同じように水道も止まる可能性があります。
数日〜数週間にわたって断水が続くケースもあります。
避難所では、給水車や配給によって水を受け取れることがありますが、在宅避難の場合は、事前の備蓄か、給水所へのアクセス手段がないと水が手に入りません。
とくに注意したいのが次のような点です:
- 給水所が遠いと高齢者や体調の悪い人にとっては水を運ぶのが負担になる
- 災害直後はスーパーやドラッグストアで水が売り切れる
日常生活の延長線で考えるのではなく、
「ライフラインが止まった前提」で備えることが、在宅避難の鉄則です。
1日に必要な水の備蓄量は季節や家族構成によって変わる
水の備蓄量はどれくらいしたらいいのか、
夏場と冬場で備蓄は変わるのか、高齢者や乳幼児がいる家庭が気をつけること
などの疑問に答えています。
災害時に必要な水の備蓄量の目安は、1人あたり1日3リットルとされています。
この3リットルには、単に飲むだけでなく、調理に使う水も含まれています。
水の備蓄量は1人1日3リットルが基本

1人1日3リットル × 7日分が、水の備蓄の基本だよ!
- 調理に使う水
- 薬の服用に使う水
など、「命を守るために必要な最小限の水」が含まれています。
なぜ「3リットル」なの?

調理や薬の服用を入れると1日の水3リットルの備蓄は最低限の安心ラインだにゃー
人が1日に必要とする水分は、気温や体調によって変わりますが、通常でも1.5〜2.5リットルの水分補給が必要とされます。
加えて、調理や薬の服用に清潔な水を使うことを考えると、1日3リットルという目安は最低限の安心ラインと考えられます。
「3日分」では足りない理由

災害の長期化や物流の遅れから、最低でも7日間分の備えが必要だにゃー。
かつては「最低3日分の備蓄」が推奨されていましたが、近年は、災害の長期化や物流の遅れを踏まえて、
「最低7日分、できればそれ以上」
が目安とされています。
とくに在宅避難の場合、配給や給水車が利用できないこともあるため、自力で水を確保できる準備が欠かせません。
「多めに備える」ことが安心につながる

「水は命そのもの」多めに備えておくと精神的に安心できるにゃー。
水は重くてかさばるため、たくさん備えるのは大変に感じるかもしれません。
しかし、「これだけあれば家族が7日間なんとか暮らせる」という備蓄は、精神的な安心にもつながります。
実際に私も、「とりあえず1週間分」「できればもっと」と決めて備えたことで、災害時への不安がグッと減りました。
水の備蓄は、家族の命を守るための第一歩。
まずは1人3リットル×7日分を目安に、少しずつ準備を始めていきましょう。
とはいえ、「3リットル×7日分」と言われてもピンとこない方も多いのではないでしょうか。

家族の人数とペットボトルのサイズ別に、必要な本数・ケース数を表にまとめましたにゃー。
参考にしてね。
次の表では、2Lボトル・500mlボトルで備蓄する場合の本数やケース数を、家族の人数ごとにわかりやすくまとめました。
自宅のスペースや管理のしやすさに合わせて、備蓄方法の参考にしてください。
家族人数別|2Lペットボトルで備える場合の目

コスパよく備蓄するなら2Lペットボトルがおすすめだにゃ。
保管スペースに余裕があり、コスパよく備蓄したいなら、2Lペットボトルがおすすめです。
ここでは、2人〜4人家族の場合に必要な2Lペットボトルの本数とケース数(1ケース=6本)を一覧にまとめました。
2Lペットボトルの場合
| 家族人数 | 必要な水の量(7日分) | 2Lペットボトルの本数 | ケース数(6本入) |
|---|---|---|---|
| 2人家族 | 42リットル | 21本 | 約3.5ケース |
| 3人家族 | 63リットル | 32本(正確には31.5) | 約5.3ケース |
| 4人家族 | 84リットル | 42本 | 7ケース |
※備蓄は「7日分+α」が理想。1〜2本多めに用意しておくと安心です。
家族人数別|500mlペットボトルで備える場合の目安

500mlペットボトルは持ち運びしやすいにゃ。
外出時や避難時のリュックに入れるのにおすすめだにゃ〜。
持ち運びやすさ重視なら、500mlペットボトルが便利です。
高齢者や子どもにも扱いやすく、外出用や避難時のリュックにも入れやすいサイズです。
こちらでは、500mlボトルで備えた場合の本数とケース数(1ケース=24本)をまとめました。
500mlペットボトルの場合
| 家族人数 | 必要な水の量(7日分) | 500mlペットボトルの本数 | ケース数(24本入) |
|---|---|---|---|
| 2人家族 | 42リットル | 84本 | 約3.5ケース |
| 3人家族 | 63リットル | 126本 | 約5.3ケース |
| 4人家族 | 84リットル | 168本 | 7ケース |
※小分けされている分、ゴミの量は増えやすいので保管時・廃棄時の工夫も考えておきましょう。
家族構成や体調によって変わる目安

高齢者や乳幼児、持病のある方は、余裕を持って備蓄してにゃ。
水の備蓄量は「1人1日3リットル × 7日分」が基本ですが、家族の年齢や体調によって必要な量は変わります。
たとえば、
- 乳幼児は体が小さくても、体調を崩しやすく水分補給がこまめに必要です。
調乳や食器の洗浄など、清潔な水を多く使う場面も多いため、余裕をもって備えることが大切です。 - 高齢者は、のどの渇きを感じにくく水分不足に気づきにくい傾向があります。
体調を崩す前にこまめな水分補給が必要です。
重たい容器が扱いにくい場合もあるので、軽いボトルや手の届く場所への配置など工夫も必要です。 - 持病のある方は、服薬のための水や体調管理のため、通常より多くの水が必要になることもあります。
また、発熱や下痢・嘔吐などの症状が出た場合にも、水分はいつも以上に消耗されます。
このように、家族構成や体調を踏まえて「余裕を持った備蓄」が重要です。
一律の量にとらわれず、それぞれの状況に応じて、余裕を持った準備を心がけましょう。
夏場・冬場の備蓄量と気をつけること

夏は汗、冬は乾燥…
季節ごとに備蓄を見直すのがポイントだにゃ!
水の必要量は季節によっても変化します。
とくに、暑い夏や寒い冬には、備え方に工夫が必要です。
夏場に気をつけたいこと

夏場は、多めに備蓄をするんだにゃー。
- 暑さで発汗量が増え、脱水リスクが高まるため、普段より多めの水分補給が必要です。
- 備蓄量は、通常より1〜2日分多く用意しておくと安心です。
- また、飲みやすい冷感ボトルや、500mlのペットボトルが便利です。
冬場に気をつけたいこと

凍結しないように保管場所に気をつけるんだにゃ。
- 寒さで汗をかきにくくなり、水分補給を忘れがちですが、暖房や空気の乾燥で体は水分を失っています。
- 備蓄水は凍結を防げる保管場所を選びましょう。
災害は季節を選ばずにやってきます。
だからこそ、季節に応じた備蓄の調整や保管の工夫が、実用的な備えにつながります。
高齢者・乳幼児がいる場合の追加の備蓄

赤ちゃんやお年寄りがいるおうちは、
ちょっと多めに水を用意しておくと安心だにゃ〜!
水の備蓄は「1人1日3リットル × 7日分」が基本ですが、高齢者や乳幼児がいる家庭では追加の備えが必要です。
高齢者の場合
- 高齢者はのどの渇きを感じにくく、自分では水分不足に気づきにくい傾向があります。
- 周囲がこまめに声をかけて、水分補給を促す工夫が大切です。
- また、軽くて扱いやすい容器(500mlなど)を手の届く場所に置くことで、
自分で取りやすくなります。
乳幼児の場合
- 乳幼児は体が小さい分、脱水症状を起こしやすいため、十分な水分が必要です。
- 調乳用や哺乳瓶の洗浄などにも清潔な水が必須です。
- 予備の水を多めに備えておくことで、急な体調不良や発熱にも対応しやすくなります。
家族構成や体調によって水の必要量は変わるものです。
家族一人ひとりの特性に合わせた
「上乗せ備蓄」を心がけましょう。
生活用水は「暮らしを支える水」その役割と必要量とは
災害時には飲み水だけでなく、トイレや手洗い、掃除といった生活用水の確保も欠かせません。
この章では、生活用水がどのような場面で必要になるのか、1日にどれくらい備えておくべきかを具体的に解説します。
ご家庭の備蓄の参考にしてください。
生活用水は、トイレ・洗濯・掃除に欠かせない「暮らしを支える水」

飲み水だけじゃなくて、
トイレやおそうじにも水は必要なんだにゃ!
生活用水とは、飲み水以外のあらゆる生活行動に使う水のことです。
災害時には、次のような場面で必要になります。
- トイレの洗浄
- 手洗いやうがい
- 食器や調理器具の洗浄
- 洗濯や掃除
- 身体拭き
これらの用途を満たすことで、健康で清潔な暮らしが成り立ちます。
生活用水は飲料水ほどの清潔さは不要ですが、最低限の衛生状態を保つことが大切です。
汚れた雨水や使い回しの水を安易に使うと、健康被害のリスクがあります。
生活用水の役割と必要量

飲み水じゃないけど、とっても大事!
生活用水は1人1日10〜20L、3日分は備えておこうにゃ。
生活用水の推奨される備蓄日数は、最低3日分を備蓄することが推奨されています。
災害直後は水道・電気・ガスなどのライフラインが止まる可能性が高いため、
まずは最低3日分の備えが基本となります。
より安心を求める場合や大規模災害(例:南海トラフ地震など)を想定する場合は、
1週間分以上の備蓄が望ましいとされています。
災害時や備蓄を考える時の生活用水の必要量は、1人1日10〜20リットルです。
この量は、トイレの洗浄・手や体を洗う・食器や調理器具の洗浄など、飲み水以外の用途を想定した最低限の目安です。
一般的にトイレの1回の洗浄には6〜8リットルの水が必要とされます。
1日数回の使用を想定すると、トイレだけでも10リットル前後が必要です。
乳幼児や高齢者、ペットがいる場合は追加で多めに準備が必要です。

高齢者やペットがいるおうちは、
ちょっと多めに備えておくと安心だにゃ。
日常生活では、1人1日200リットル以上の水を使うこともありますが、災害時はできるだけ節水を心掛けてください。
家族構成や期間に合わせて十分な備蓄を心掛けましょう。
生活用水の確保方法|家庭でできる実践例

お風呂の残り湯やポリタンク活用で、
生活用水もちゃんと備えられるんだにゃ!
生活用水は、飲料水と比べて「水質の清潔さ」はそれほど厳しく求められませんが、
最低限の衛生状態は必要です。
ここでは、災害時に生活用水を確保するための具体的な方法をご紹介します。
・浴槽やバケツに水をためておく
地震などの災害時、断水の可能性を考え、揺れが収まったらすぐに風呂やバケツ、シンクに水をためておくことが推奨されています。
• ポリタンクや折りたたみ式タンクの準備
ポリタンクや折りたたみ式水タンクは運びやすく、大容量の生活用水を確保するのに便利です。
タンクは劣化やひび割れに注意し、定期的な点検が重要です。
• ペットボトルなどの空き容器を再利用
密閉できる容器に水道水をいっぱいまで入れて、直射日光を避けて保管することで、
数日間の生活用水を備蓄できます。
• 公園や地域の井戸、手押しポンプの活用
地域には災害時のために井戸や手押しポンプが設置されている場所もあり、それらを利用して水を確保する方法もあります。
• 浴槽の水を残しておく
普段からお風呂の水はすぐに抜かず、生活用水としてストックしておくのも有効な手段です。
浴槽には一般的に150〜200Lの水がためられます。
(注)小さなお子さんがおられるご家庭は注意が必要です。
まとめ|水の備えは「命を守る準備」まずは少しずつ始めよう

ちょっとずつの備えが、いざというときに大きな安心になるよ!
災害時に一番困るのは「水の不足」です。
飲料水だけでなく、トイレや手洗いなどに使う生活用水も欠かせません。
備蓄の基本は
「1人1日3リットル × 7日分」
さらに、生活用水の量として1日10〜20リットルの備えがあると安心です。
高齢者や乳幼児がいるご家庭では、体調や生活に合わせて追加の備えも必要になります。
水の備蓄は「いざというときの安心」に直結します。
私自身、夫の体調管理や在宅避難を考えるようになってから「水を備えること」の大切さを実感しました。
小さな備えが、大きな安心に変わります。ぜひ今日から始めてみてください。